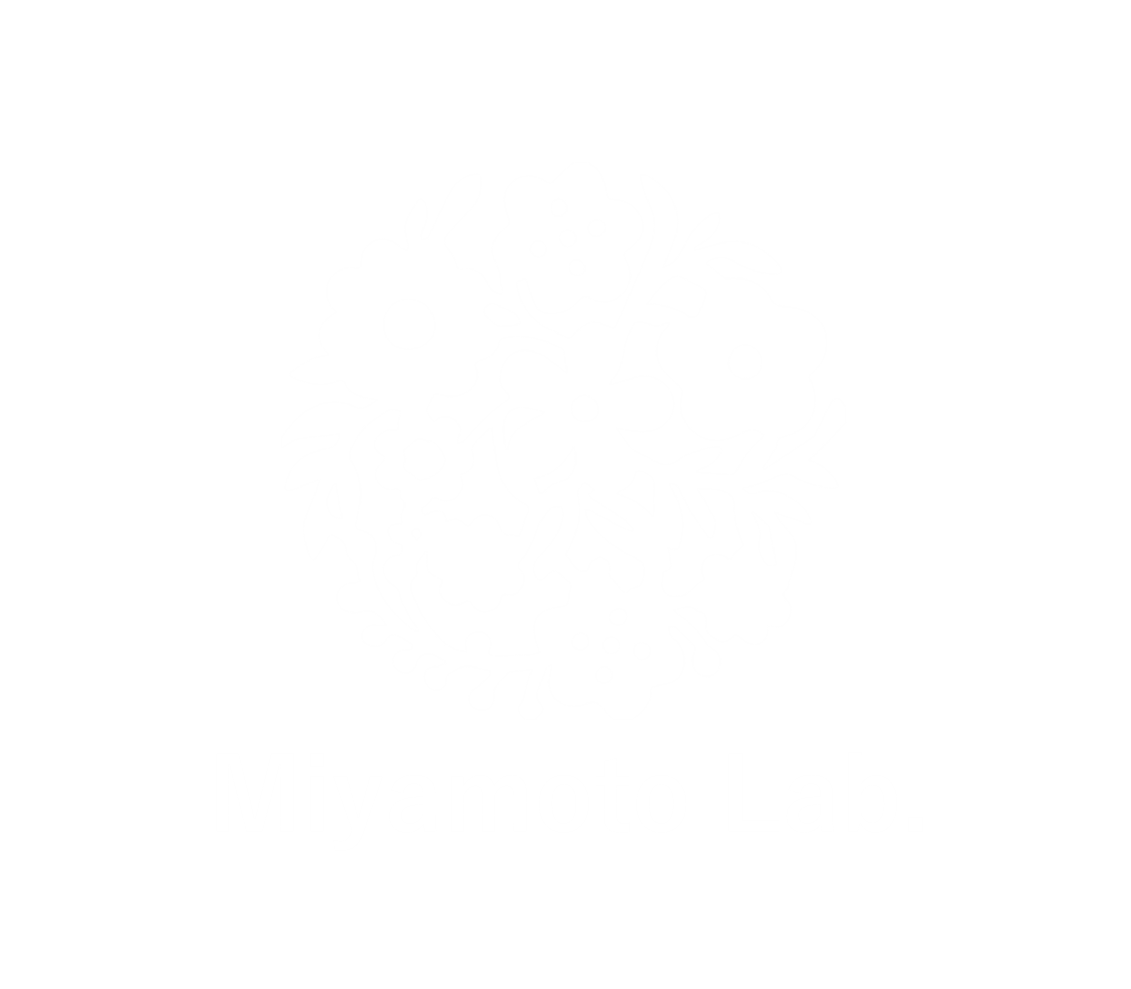Self introduction自己紹介
| 卒業研究として.有明海沿岸低平地に堆積する重粘土の透水性に関する研究に取り組んだことを機に,粘土コロイドと土中溶液中の溶質との相互作用に起因する界面動電現象に関心を持つ。ところが,重粘土を調べようにもあらゆる土壌センサー技術が通用しないことに気付き,米国農務省・塩類研究所(Salinity Laboratory)への研究留学を機に新たな手法の導入を目論む。しかし,「10年かかるぞ!いつまで学生でいるつもりだ?」というラボのレジェンド(van Genuchten博士)の意見を真摯に受け止め,それを断念する。 しかし,ポスドク時代に「重粘土を測る」という前人未踏の課題への未練が再燃し,複数の大学・研究機関を渡り歩きながら様々な技術を取り込みつつ,土を測る技術の開発・応用に一貫して取り組み,本コミュニティの運営メンバー・平嶋の偶然の産物がきっかけとなり,ついにマイクロ波を利用した重粘土の水分・溶質非破壊計測技術を確立することに成功。世界の粘質土の中で起きていることが,これから明らかになる・・・と嬉しそうに話している(らしい)。 土壌・土木関連分野ではいち早く時間領域透過法(TDT),宇宙線土壌水分観測システム(COSMOS),統合型IoTプラットフォーム,人工知能(AI)による土壌環境予想技術等の先端技術開発に取り組むとともに,土を測る技術に関する多数の研究論文・解説等を発表。2015年土壌物理学会大会シンポジウム「進化する土壌水分計測」の企画や,「改定6版 農業農村工学標準用語辞典(2019年8月)」において土壌水分・塩分計測に関する用語説明等も担当。佐賀大学に着任後は,「最恐のブラック研究室」と多くの学生達に恐れられる研究室を主催。多くの学生らに敬遠されながらも,「1割の学生にウケれば,それでよい」というポジティブ思考のもと,気力・体力に満ちた若者らとともに,農研機構・東北農業研究センター・福島研究拠点で学んだ「有機農法の経験」を生かして水稲栽培を行いつつ先端技術開発を行うという異色の教育研究を展開している。 苦しかったポスドク時代に,福島の雄大な風景とそこで農業に勤しむ人々の温もりに触れ,ポスドクが陥りがちなフォースのダークサイドから解放・浄化され,「明るく,楽しく研究者として生きよう!」と決意。東日本大震災を契機に土にまつわる自然災害研究にも手を広げ,最近は,熊本県出身者を中心とした有志を募り,熊本地震によって傷ついた阿蘇地方に我が国第1号となるCOSMOSや,企業と共同開発した統合型IoTプラットフォームを用いたビッグデータ観測網を構築しつつ,地域社会・地域生活者に寄り添った農学教育・研究の在り方を模索している。 「サラリーマン金太郎,頭文字D,Blue Giant」等を教科書と称して学生らに薦める昭和男子。スクエニの某ネトゲ全国ランク1位の元ギルマス。「ホリエモンが言っている・・・。戦略的無能ってチートすぎる・・・。異世界でスローに生きたい・・・。」等が最近の口癖(らしい)。 |